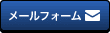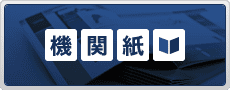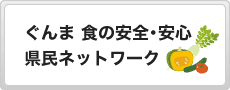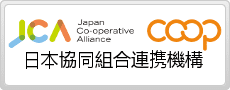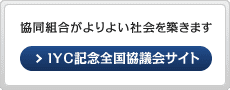平成29年度関東ブロック地方消費者フォーラム(前橋市)に
県内外から264名が参加、消費者のための連携・協働を確認しました
県内外から264名が参加、消費者のための連携・協働を確認しました
平成29年度関東ブロック地方消費者フォーラムが2月15日(木)群馬県生涯学習センター(前橋市)で開催され、県内外から264名が参加して学習と交流を深めました。
関東ブロック地方消費者フォーラムは、関東甲信越都県で毎年持ち回り開催されているもので、今年度は群馬県での開催となりました。群馬県生協連は、消費者庁・群馬県と県内28団体で構成する実行委員会(実行委員長吉野晶弁護士)に加わり、県消費者団体連絡会とともに事務局団体としての役割を担いました
関東ブロック地方消費者フォーラムは、関東甲信越都県で毎年持ち回り開催されているもので、今年度は群馬県での開催となりました。群馬県生協連は、消費者庁・群馬県と県内28団体で構成する実行委員会(実行委員長吉野晶弁護士)に加わり、県消費者団体連絡会とともに事務局団体としての役割を担いました


続いて消費者庁東出浩一審議官が「消費者問題を解決する、起こらないようにするためには行政の取り組みも重要だが地域の対応力を高めていくことも大事で、そのために地域で活動されている方々がより連携して協働していくことをめざして地方消費者フォーラムを開催してきた」とあいさつし、消費者庁の取り組みについて説明しました。
群馬県からは、生活文化スポーツ部五十嵐優子部長があいさつに立ち、「平成28年度の群馬県内の消費生活センターに寄せられた相談件数は1万7千件。高齢者への悪質な販売、インターネットに関するトラブルが多く、振り込め詐欺などの被害も年々増加している」と消費者被害の実態を報告。「消費者団体や事業者と国や県、市町村との『連携・協働』が消費生活の向上につながると強調し、「富岡製糸工場など群馬の歴史と自然にも親しみ足を運んでほしい」と呼びかけました。
群馬県からは、生活文化スポーツ部五十嵐優子部長があいさつに立ち、「平成28年度の群馬県内の消費生活センターに寄せられた相談件数は1万7千件。高齢者への悪質な販売、インターネットに関するトラブルが多く、振り込め詐欺などの被害も年々増加している」と消費者被害の実態を報告。「消費者団体や事業者と国や県、市町村との『連携・協働』が消費生活の向上につながると強調し、「富岡製糸工場など群馬の歴史と自然にも親しみ足を運んでほしい」と呼びかけました。

舟木弁護士
基調報告では消費者支援群馬ひまわりの会理事舟木諒弁護士が「適格消費者団体の活動・行政や市民との連携を目指して」と題して講演し、2月5日に群馬ひまわりの会が全国17団体目の適格消費者団体に認定されたことを報告したうえで、適格消費者団体と市民、行政との連携についてお話ししたい、と切り出しました。
舟木氏は、消費者被害は、同種の被害が多数発生するというのが特徴で、被害の認識がない場合や泣き寝入りしてしまう場合も少なくなく、潜在的な被害が多い、と指摘しました。そのうえで、消費者個人の救済をしても被害は継続してしまう、事業者の「不当行為」「不当条項」の差し止め行うことのできる団体として、適格消費者団体の導入がされたと制度の意義を強調しました。
その後、レンタル事業者や自動車販売業者などの具体的な事例を紹介しながら、全国の適格消費者団体や群馬ひまわりの会の活動を報告していきました。
舟木氏は、消費者被害は、同種の被害が多数発生するというのが特徴で、被害の認識がない場合や泣き寝入りしてしまう場合も少なくなく、潜在的な被害が多い、と指摘しました。そのうえで、消費者個人の救済をしても被害は継続してしまう、事業者の「不当行為」「不当条項」の差し止め行うことのできる団体として、適格消費者団体の導入がされたと制度の意義を強調しました。
その後、レンタル事業者や自動車販売業者などの具体的な事例を紹介しながら、全国の適格消費者団体や群馬ひまわりの会の活動を報告していきました。

基調報告のあと昼食をはさんで、4つの団体から取り組み実践報告がされました。

前橋市消費生活啓発員の会は、6名による寸劇「それゆけ!まえばし出前講座~悪質商法に気をつけよう~」を披露しました。悪質リフォームの勧誘、強引な買取商法などの手口を、啓発員の熱演で楽しくわかりやすく伝えました。寸劇はますます巧妙になっている悪質商法の被害を未然に防ごうと、消費生活センターに寄せられた情報をもとに再現劇にして啓発を行っているものです。同会は、平成28年に「ベスト消費者サポーター章」を受賞しました。

消費者行政充実ネットちばの拝師徳彦事務局長、佐久間実幹事は、「消費者行政活性化シンポジウムの取組」について報告しました。(以下要旨)ネットちばでは「地域連携」、住民の声を行政に届ける取り組みとして住民の市町村シンポを開催しています。県内12箇所で開催、行政から諸団体へ声掛けしてもらい、実行委員会をつくって4~5回の会議を開いて実施しています。これをきっかけに地域協議会を立ち上げた地域もあります。また、リコールキャンペーンを地域と協力しながら実施し、制度の理解やリコール製品の回収に取り組んでいます。

事例報告を聞いたあと、参加者は32のグループに分かれて「消費者市民社会を築くために私たちができること」をテーマに分散交流会を行いました。各グループで基調報告や事例報告、自らの問題意識など熱心な意見交換が行われました。各グループのテーブルには、実行委員団体であるコープぐんまとパルシステム群馬の2つの生協からお菓子の差し入れがあり、参加者に好評でした。

分散交流会を終え、参加者は再び全体会場に集まり、代表して4つのグループから「企業の方が営利に関係なく見守り活動をされているのがわかって頼もしいと思った、前向きに被害の未然防止に取り組んでいる姿がわかってもっと連携していきたい」「埼玉県でつくられたインターホンの横につけて悪質訪問販売を撃退するツールが紹介された、おれおれ詐欺防止では試しに親に電話をかけてみる、合言葉を決めておくなどの対策が大切と話された」「各県の適格消費者団体づくり、地域協議会づくりの交流ができた」「消費者被害にこれだけ警鐘を鳴らしていても少なくならないのか、身近な人に相談できる関係をつくっていかなければならない、一人ひとりが発信していこう」などの発表がありました。
発表者は、3グループ鈴木厚子さん(大泉町消費生活センター消費生活相談員)、17グループ小林祐太さん(パルシステム群馬センター長)、22グループ今野嘉久さん(埼玉県消費者団体連絡会事務局)、29グループ本郷高明さん(食とみどり、水を守る群馬県民会議副議長)のみなさんでした。



続いて東出審議官から「適格消費者団体についてのご理解を深めていただけたと思う。事例報告も寸劇は名演で、有意義な経験を聞くことができた。他のブロックと比べると少人数の分散交流会でお菓子も用意されていたが、食べる間もなく交流されていた。はじめて話を聞いたとの報告があったが、そうしたことが新しい連携・協働につながっていくものと思う。ぜひ今後の活動につなげてほしい」と講評がありました。

フォーラムの閉会にあたり、群馬県消費者団体連絡会坂本棟男副会長から、「消費者をめぐる状況は難しい局面にある、お互いに問題点を共有することができた。これを機に、さらに地域や職場で消費者市民社会を実現するためにお互いに手を携えてがんばっていきたい。ご参加いただいた方、県内や各都県の実行委員の方々に感謝します」とあいさつがありました。